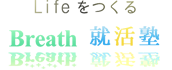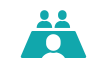【レポート】新しい学びのかたち~表現教室はじめました~
2019.10.15
お役立ちコラム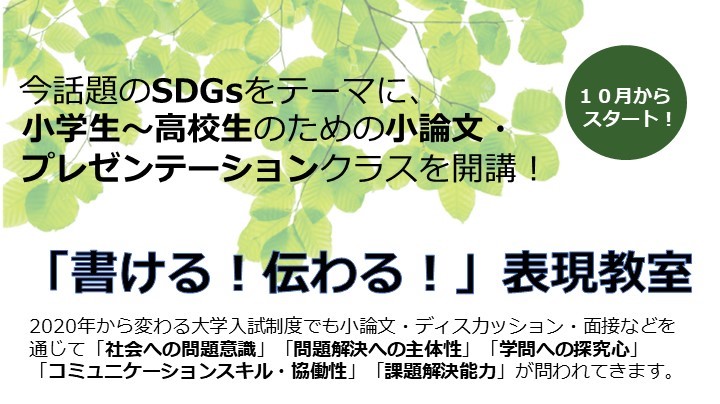
表現教室をはじめるにあたり
こんにちは、Breath代表の本多です。夏休みに単発の表現教室として、作文やプレゼンテーションクラスを開講しました。この表現教室は、これからの時代に求められる論理的思考力、そしてそれを表現する力を養うべく、来年からの教育改革を前にスタートしたものです。
そしてこの秋からは8回講座として深く考えられるクラスでやってみることにしました。多様なジャンルを扱うことのできる「SDGs」をテーマにし、子どもたちが自分でテーマを設定していきます。
また、小学生から高校生まで、学年の境を設けることなく皆で考えるクラスにしたこともポイントです。現に今通ってくれている生徒さんは中学生と小学生。コミュニケーションにまったく問題はなく、一緒に互いのテーマについてディスカッションをし、アイデアを出し合っています。
先日講演会を拝聴し、オランダのイエナ・プランを学びましたが、そこでも小学校は3学年が同じクラスになるそう。互いが助け合い、子どもたちは年下の子に対して「teachではなくsupport」をするのだと主体的に言っていたとのこと。考えてみれば日本でも学年で管理されるのは学校まで。社会に出たらそんなことはありませんよね。人と人とのコミュニケーションが取れるようになるには、日頃から多世代の交流が大切だと考えています。
講座の最後には発表会を設け、きちんと場数を踏んでもらいます。そこでの発表資料を作る体験も、PCスキル向上に繋がります。ただ、中身を重視したいので今回はデザイン等細かくこだわりませんが、次の「もっとやってみたい!」に繋がっていったらいいなと思っています。
発表会後はやったらやりっぱなしではなく、翌週の最終回で振り返りを行うこともポイントです。今からすでに発表には恥ずかしさがあふれる生徒さんたちですが、今のうちにいろんな経験をして、好奇心・向上心を刺激しながら過ごしていってもらいたいです。
2回分の授業を終えて
最後に、すでに金曜クラスは2回分が終了したのでその様子をお伝えします。
初回はまずSDGsとはなんぞや?から始まり、興味津々な生徒さんたち。まっさらなノートを渡し、今回の学びの流れ、SDGsとは、日々感じている課題を次々書き込んでもらいます。
日々感じている課題は何でもいいよと言ったのですが、2人とも環境問題が多く出てきたことに驚きました。小学生でも中学生でも、おそらくは授業でたくさん触れているのでしょうね。共通して海洋プラスチック問題が出てきたのもびっくりです。きちんと感度をもって授業を受けているのだなと思います。
また、煽り運転やいじめ、英語の授業で読んだ貧困問題等、日頃見聞きするものにどう興味を持っているのかが伝わってきます。思考を整理するうえで、このようにまず全部アウトプットしてもらうというのは見ているこちらも面白いです。何が好きなのかなという、将来に繋がる部分にも見えます。
「何も出てこなくなったら、主人公を決めるといいよ」
このアドバイスにまた刺激を受ける生徒さんたち。止まっていた手がまた走り出します。このようなアイデア出しのコツもお伝えしていきます。
そして今度はSDGsの中から自分の興味のあるものを3つ選び、中心にテーマを置き、関連するワードを蜘蛛の巣のように繋げて書き出してみます。これもまた、想像する力を鍛えるやり方です。思いもよらぬ方向に話が広がっていくのもまた面白いです。
2回目は自分自身のテーマを決定し、深掘りを始めます。それぞれ悩みながらも、「教育と貧困」「いじめ」をテーマにすることを決めました。書きやすいこと、考えてみたいこと、優先順位をつけて選びました。
ここで小論文とは何か、作文との違いを説明し、例として私の大学入試の問題と書いた論文の構成を伝えます。大人でもびっくりするようなお題だと思うのですが…
「自由とは何か、具体的な例を用いて論ぜよ」(1万字)
です。笑 これには私も仰天しました。そこで前回伝えた主人公決め、私は教育に興味があったので「子どもと自由」とすることにし、ちょうど当時問題になっていた少年犯罪と少年法の厳罰化について書いてみることにしたのです。
ここで、自由にはfreeとlibertyという2つの意味があるんだよ、ちなみに自由の女神はlibertyねと話すと、生徒さんたちは目がまんまるに。そこから、言葉の使い方、きちんと辞書で調べることの重要性を実感します。この日はさらっと使った「平等」という言葉について、「平等・公平・公正」を辞書で調べることもやってみました。何でも調べろと言われますが、直面することで大切が分かりますね。
こんな風にして、多様なことに触れながらクラスが進んでいきます。
ちなみに宿題は出していません。麹町中学の手法としても最近話題ですが、私自身宿題はなくても良いと思っています。クラス内ですべてやりきることに重きを置いて欲しい。特にこれはすべての学びのベースとなる場であり、帰ってからは本を読んだり、家族と話したり、そんな中で「あっこれ小論の中で扱えるかも!」といった気づきに繋げてもらいたいのです。
3回目のためにぜひ図書館で本を借りてきてねということだけお願いをしました。論文づくりに本は欠かせません。次回は本の読み方・調べ方もお伝えしていく予定です。
この新しい学びにご興味を持っていただけたらとても嬉しいです。発表会に間に合う短縮版クラスも用意させていただきましたし、今後もクールを設けて実施していきたいと思っています。何回参加しても毎度違うテーマを設定するだけで良いので、成長を実感でき、知的好奇心をくすぐるはずです。一緒に学べる仲間を待っています。